
胃腸の病気・不調への対応

胃腸の病気・不調への対応
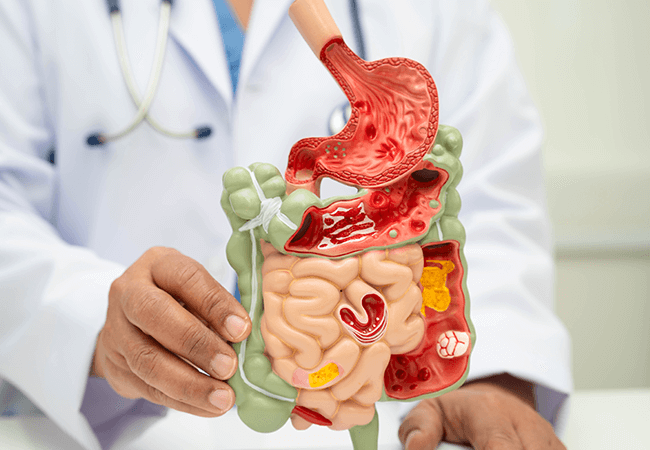
胃痛を含めて様々な腹痛や、慢性的な便秘、下痢、お腹のもたれ感、張り感など、「お腹の調子が悪い」と感じる方は多いと思います。それらは色々な原因によって起こりますが、原因が分からぬまま何度も症状を繰り返したり、「仕方ない」と放置されていたりすることも多いかと思います。これら不調を訴える方の中には、胃癌、大腸癌、食道癌といった放置すると命に係わる危険な病気の方もいる一方で、下記にお示しする機能性ディスペプシアのような、危険はないが不快な症状が長く続く病気・不調もあります。
まさにケースバイケースで、原因によって望ましい対応法も違ってきます。診察や各種検査によってそれらを適切に見分け、最も良い治療法を選んで早期に始めることは重要です。「良く分からないけど何となく胃薬を飲んでいる。でもいつも調子が悪い」といった状態から抜け出せるよう、医師としてお手伝いしたいと思っています。
明らかな炎症や潰瘍などが無いにもかかわらず、上腹部に痛み・不快感(胸やけ、もたれ)を起こす病気のことです。胃という臓器は、食事や空腹時など状況に合わせて収縮・弛緩といった動きをしていますが、自律神経の不調などでそれが適切に行われなくなると、上記のような症状を起こすことがあります。また多くの場合、感覚を伝える神経が過敏になること(知覚過敏)も相まって、症状を強めます。こういったメカニズムで起きる病気を機能性ディスペプシアと呼びます。胃の炎症や粘膜の荒れとは違う病気です。
馴染みのない病名かも知れませんが、非常に多くの方がこの病気に苦しんでいます。いわゆる「胃の不調」を訴えて病院を訪れる人の約50%は、実は原因が機能性ディスペプシアであったというデータがあります。また全人口のうち10~15%がこの疾患に相当する、とも言われます(例えば従業員100人の会社だとその内10~15人の社員はこの病気で悩んでいる、ということです)。
この病気の場合、胃内視鏡を始めとする各種検査を行っても、症状に繋がるような異常は見つかりません。そのため、「異常ありませんから大丈夫です」とか「(症状の主原因ではないが)軽い胃炎ですから、胃薬を飲んでおいてください」という説明を受けて、そのままになってしまう、つまり症状が改善しないケースが多いです。
残念ながら特効薬と言える薬はないのですが、まずはどういった病気か理解をしていただき、次にいくつかの薬を試していくことで症状の改善が得られることは多いです。
ちなみに、以前いわゆる「神経性胃炎」「ストレス性胃炎」などと呼ばれていた方の大部分がこの病気に相当しますが、「胃自体には炎症がないのに、それを『○○胃炎』と呼ぶのはおかしい、紛らわしい」ということで、この名称が用いられるようになりました。
上記の機能性ディスペプシアと似て、自律神経の不調が原因で腸の動き(蠕動運動)が乱れる病気です。知覚の過敏も伴っていることが多いです。腹痛や腹部膨満感の他に、下痢、便秘といった便通異常を起こしているケースが、この過敏性腸症候群と呼ばれます。内視鏡など各種検査を行っても、これといった異常は見つかりません。頻度のとても高い病気で、全人口の10%位の方がこの病気に相当すると言われています。
下痢を主体とする下痢型、便秘を主体とする便秘型、それらの混合した混合型などがあります。それらの型や症状に合わせて薬を選択し、内服していただきます。治療により、多くのケースで症状の改善が見られます。
以上、「機能性ディスペプシア」「過敏性腸症候群」はその発症メカニズムがとても似ており、はっきり区分できない場合や両者を合併しているケースがしばしばみられます。そのため、この2つやそれに似た病状をまとめて「機能性消化管疾患」あるいは「機能性胃腸症」と呼ぶこともあります。
時代と共に減りつつはありますが、まだまだ侮れない病気です。胃や十二指腸(胃に続く部分)に、口内炎のような粘膜の削れた部分が生じる病気です。持続的な痛みの他、時に吐血や多量の黒色便といった形で発症することがあります。
発生する原因は主に、
治療はもちろんですが、予防も重要で、①の場合は除菌が必要です。また、頭痛、腰痛などのため②鎮痛解熱剤(ロキソニン、イブプロフェンなど)を継続的に使用している方は実際多いと思いますが、これら薬の継続使用者を集めて内視鏡検査を行ったところ、その約20%に胃潰瘍が見られた、という報告もあります。これら鎮痛解熱剤が起こす胃潰瘍を予防するためには、それなりに強力な胃薬(PPI)が必要で、一般によく用いられている胃粘膜保護剤(普通の胃薬)では潰瘍予防効果が乏しいです。「胃薬を一緒に飲んでいるから大丈夫だと思っていたが、実はそうではなかった」というケースもありますので、ご相談いただければと思います。
主に幼少期に口から体内に入り、胃の粘膜に定着します。この菌は、胃の防御機能を壊し、慢性的な胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を引き起こす原因となります。さらに、感染が続くことで、胃癌発生のリスクも高まります。幸いにも、ピロリ菌は抗生物質を含む3種の内服薬同時使用で除菌が可能です。この除菌治療により、胃癌の発症リスクを1/3程度に低減させることができます。
酸性の胃液(胃酸)が継続的に食道に逆流し、食道の粘膜に炎症を引き起こす病気です。胸やけ、みぞおち付近の鈍痛・不快感などを起こすことが多いです。夜間就寝中に一定時間以上、胃液が食道に逆流・滞留していると、食道粘膜に炎症が生じてしまいます(一時的に数回胃液が逆流しただけですぐ食道が荒れるわけではありません)。この状態を逆流性食道炎と呼び、内視鏡検査で診断できます。ただし、一口に逆流性食道炎と言っても重症度は様々です。中等度以上の食道炎症、もしくは軽度炎症でも自覚症状があるケースには、内服薬による治療を行います。内服治療は多くの場合、非常に効果的で即効性もあります。逆流性食道炎のみが原因であれば、症状も短期間で消失することがほとんどですが、そうならない場合には機能性ディスペプシアなど他の原因も考える必要があるでしょう。一方、食道の炎症が軽微なケースでは、この診断名がついていても薬による治療は行わないことが多いです。人間ドックで胃内視鏡を行ったら、「逆流性食道炎」という診断名が書かれていた(かつ、判定は「経過観察」だった)という方も多いと思いますが、治療対象となるかどうかは食道炎の重症度次第です。内視鏡検査では、ごくごく軽微な食道炎でも拾い上げて指摘することが多いため、全受診者の半数以上にこの病名がついていることも珍しくありません。
一部を除き、大多数の胃癌はピロリ菌感染が起こす胃の慢性炎症で発生します。癌が大きくなるまで無症状のことがほとんどで、早期発見には内視鏡検査が有効です。早期癌のうちに発見することで、開腹手術を避け体への負担の少ない内視鏡治療(内視鏡的粘膜切除や腹腔鏡手術)で治すことができます。
ピロリ菌感染の有無、胃粘膜萎縮(粘膜が劣化していること)の有無の2要素で胃癌発症の危険度を判定することができ、ABC検診と呼ばれます。最近では中野区をはじめ各自治体のがん検診にも用いられています。胃癌リスクの高いB、C、D群判定の方には胃内視鏡検査をお勧めします。
中高年の男性に多い癌で、特に喫煙と多量の飲酒をする方は発症の危険が高いです。無症状の早期癌のうちだと、内視鏡治療で治すことが可能なこともあります。ただし、症状の現れる進行した癌では、非常に負担の大きな外科手術や放射線治療、抗癌剤治療が必要になります。また進行した食道癌は転移・再発がとても多く、危険な癌と言えます。そういったことから、前述のようなリスクの高い方には、無症状でも内視鏡検査をお勧めしています。
近年増えてきている癌で、(直腸癌も含めると)日本人のかかる癌の中では最も多い癌です。胃癌の発生頻度を上回ります。診断には大腸内視鏡検査が有効です。ただし、胃の内視鏡検査に比べると体への負担がやや大きいため、検診では便の検査(便潜血反応)を行い、陽性の場合には内視鏡検査を強くお勧めしています。早期に発見することで、内視鏡を用いた粘膜切除で根治することが可能です。
TOP